ポール・オースターを読む 『スクイズ・プレー』から『ティンブクトゥ』まで
- 2022/11/20
- 文学(海外), 読書
- Paul Auster, The New York Trilogy, わがタイプライターの物語, インヴィジブル, オラクル・ナイト, サンセット・パーク, シティ・オヴ・グラス, スクイズ・プレー, ティンブクトゥ, トゥルー・ストーリーズ, ナショナル・ストーリー・プロジェクト, ニューヨーク三部作, ハードボイルド, ヒア・アンド・ナウ, ブルックリン・フォリーズ, ポール・オースター, ポール・オースター詩集, ポール・ベンジャミン, ミスター・ヴァーティゴ, ムーン・パレス, リヴァイアサン, 偶然の音楽, 内面からの報告書, 写字室の旅, 冬の日誌, 壁の文字, 孤独の発明, 小説, 幻影の書, 幽霊たち, 最後の物たちの国で, 松岡正剛, 柴田元幸, 消失, 田口俊樹, 畔柳和代, 空腹の技法, 翻訳, 詩集, 鍵のかかった部屋, 闇の中の男
- コメントを書く

http://blog.livedoor.jp/honmashunji/archives/44011327.html
コメント
この記事へのトラックバックはありません。








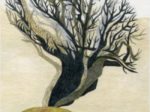























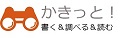
この記事へのコメントはありません。